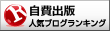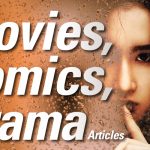セ・リーグDH導入が残念な件。2027年シーズンからのスタートが正式発表されたけど、投手が打席で食らいつく姿が好きだったんですよね。セとパで野球の違いがあってもいいじゃんと思ってた

プロ野球セントラルリーグのDH制導入が正式発表された。
セ・リーグがDH制導入を電撃決定 2027年シーズンから…投手力向上やスラッガー育成などプラス面多数
記事はこちら▼https://t.co/X9fy4NUjTq— スポーツ報知 (@SportsHochi) August 4, 2025
セ・リーグの鈴木清明理事長は「新たなセ・リーグの野球に挑戦する時期」とコメント、2027年シーズンからの導入となる。
記事によるとセ・リーグのDH制導入については2016年ごろから議論が続いていたとのこと。
近年はMLB、国際大会の他に大学や高校でもDH制導入が発表されており、唯一セ・リーグだけが“投手が打席に立つリーグ”として取り残されていた。
またセ・パ交流戦で毎年パ・リーグの圧勝に終わること、スラッガー育成や投手のコンディション維持の観点からもDH制導入を求める声が大きくなっていたとか。
セ・リーグのDH導入は近年の流れを見れば必然ではあった。でも、実は残念なんですよね…
セ・リーグのDH導入については割と前からファンの間でも希望する声が多く、なおかつ近年の流れを考えればいずれこうなるだろうとは思っていた。
ピッチクロックや申告敬遠等、合理性が重視される中でセ・リーグだけが拒否し続けるわけにもいかなかったのではないか。
またちょろっと見た限りでは現役投手も概ねDH制導入を歓迎している印象。
やはり打席に立つ、長時間塁上に居続ける、全力疾走する等は長いシーズンを乗り切る上で負担が大きいと想像する。
ソフトバンクがパ・リーグ優勝。2年連続21回目。シーズン終盤の勝負強さはまさに王者だった。新庄剛志「ソフトバンクが3連敗すれば」→翌日から怒涛の4連勝でマジックゼロ。あの発言が影響してないわけがないよね
そして、実を言うと僕はセ・リーグのDH制導入に反対だったりする。
導入が正式に決まったので今さら反対もないのだが、要するに残念である。
藤浪晋太郎が初勝利。中日が2戦連続で主力を出さず左打者だらけの打線を組んだことへの感想を。井上監督「ベストオーダーを組めない」、藤浪「好きなだけ嫌がってください」。真剣勝負の最中に日和って自分で弱点晒してんじゃねえよ
投手が打席でがんばる姿が好きなのよね。野球は打って守って投げて走ってのスポーツですよ
表題の通りだが、僕は打席でがんばる投手を観るのが好きである。
打撃が専門ではない選手(投手)が打席で足掻く、少しでも球数を投げさせようと粘る、あわよくばヒットを打ってやろうと食らいつく姿がめちゃくちゃ好み笑
もちろん最近噂のゴキブリ野球というか、前に飛ばす気のないファール狙いはダメ。
あんなものは見苦しいだけで視聴側としても苦痛でしかない。
そうではなく、チャンスでどうにかバットに当てようとがんばる、自分を助けるためにヒットを狙う、一塁まで全力疾走する光景が好き。
やはり野球は打って守って投げて走ってのスポーツ。
投手のコンディションやスラッガー育成、編成どうこうよりも「野球は9人全員が打ってナンボでしょ」という思いが強い。
現役時代の桑田真澄が「1回や2回全力疾走したくらいでピッチングが乱れるようじゃエースとは言えない」とコメントしたらしいが、なるほど、いいことを言いやがる笑
佐藤輝明と阪神の交渉が難航。2026年オフにポスティング制度でMLB移籍? でも佐藤輝明のメジャー挑戦のタイミングは“今”だよな。2025年シーズンにいい感触を掴んだ
セとパで野球が違うのも悪くない。チャンスで投手に打席が回ってくるときの駆け引きは野球の醍醐味
またセ・リーグとパ・リーグで野球が違うのもそこまで悪くないと思っている。
よく聞くのが投手が打席に立たないパ・リーグは先発が長い回を投げるケースが多い、投手交代の自由度が高いというもの。
逆に言うと(投手に打席が回る)セ・リーグは投手交代が早い傾向があると。
またDHに打撃専門職を起用することで攻撃の幅が広がる側面もある。
守備が下手な“打つだけの鈍足マン”にとってはセ・リーグよりもパ・リーグの方が活躍できる可能性が高まる。
巨人を退団→ロッテに行ってHR王になったグレゴリー・ポランコなどはその典型である。
たとえばだが、横浜DeNAベイスターズのタイラー・オースティンは打撃は凄まじいが、その反面怪我が多い。守備で必要以上にがんばってしまうのが主な要因だが、DH制があれば離脱はグッと減るはず。
それらを踏まえた上で。
僕は投手が打席に立つことによるやりくりを楽しんでいる。
チャンスで投手に打席が回る→代打を出すか、そのまま打たせるかの選択。
代打の切り札を出したところで相手が投手交代→代打の代打を出すという苦渋の決断。
これらのベンチワークは野球観戦の醍醐味だと思っている。
確かに交流戦ではパ・リーグの物量に押されっぱなしだが、ああいうベンチ同士の駆け引き、化かし合いの要素が薄れてしまうのは残念である。
そもそも無理やり他と足並みを揃える必要があるの?
国際大会でも各国の特色があるようにリーグごとに野球が違うのがおもしろいんじゃないの?
クライマックスシリーズ(CS)のアドバンテージ見直し案。反対意見が多数だけど僕は賛成なんですよね。2024年のDeNAの下剋上は胸糞が悪かった
もちろん老害発言をしている自覚はある。
やる気ゼロの打席を観なくて済むメリットはある。無気力に三振する姿にクッソ萎えるんですよね
DH制導入のメリットとしては、投手のやる気ゼロの打席を観なくて済むというのがある。
試合展開によって“投手が打つべきではない”局面は必ずくる。
たとえば6回あたりで4、5点差、2アウトで投手に打席が回ってきた場合は無理にバットを振る必要はない。
下手にランナーに出たり変な打ち方をして手が痺れたりといったリスクを冒すよりもピッチングに専念するべき。
攻撃陣にとっても次の回は1番からスタートできることを考えれば素直に凡退してくれた方がメリットがある。
ただ、それ以外の場面。
同点や1点差で回ってきたときは打たないよりも打った方がいいに決まっている。
たとえ確率が低くても何かを起こしてやろうとがんばる姿が好きだとも申し上げている。
ところがそういう場面でいっさい打つ気を見せない、適当にバットを振ってさっさとベンチに戻る投手がいる。
たとえば横浜DeNAのトレバー・バウアーがそれに当たる。
もともとバッティングが得意ではない、走塁等で疲労するよりピッチングに集中する方がいいという考えなのだと思うが、ああいう無気力な姿にはとにかく萎える。
あんな光景を見せられるくらいならDH制の方がはるかにマシ。
打撃がダメダメな8番キャッチャー→無気力な9番ピッチャーという連続自動アウトはガチの地獄である。
僕がMLBを観なくなった理由。単純につまらないよね。熱量がなさすぎて。イチロー「データ偏重によって頭を使わなくてもできる野球になってる」
そんな感じでセ・リーグのDH制導入には(僕にとって)いい面と悪い面がある。
どちらかと言えば残念だが、同時にセ・リーグの野球がどう変わっていくかには興味がある。
もしかしたらピンチランナーや守備固めの起用法も変化があるかもしれませんね。
大谷翔平背番号17 野球 Tシャツ ジャージ ユニフォーム 野球ユニフ半袖
侍ジャパン 番號18 山本 由伸 野球応援 フェイスタオル
今永昇太のピッチングバイブル