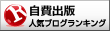夏の甲子園(2025年)振り返り。送りバントを多用する理由が興味深い。「チャンスを広げるというよりダブルプレーを避ける意味合いが強い」んだって。今後内野守備の重要性はさらに高まるのでは? 才能がモノを言う投手力、打撃力より上達しやすい

2025年8月1日からスタートした第107回夏の甲子園。
8月23日に沖縄尚学の初の夏優勝で幕を閉じたわけだが。
何度か申し上げている通り僕は広陵高校の暴行事件をきっかけにドハマりした。
数日経った今も余韻に浸っているのだが、下記の振り返り記事がなかなか興味深かった。
夏の甲子園 “新たな時代に見えてきた課題”【解説】https://t.co/BKy6y0vaAC #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) August 23, 2025
今大会で導入された2部制の効果や課題、SNS時代の対応の難しさといった内容の記事。
SNS上のコメントでは広陵高校関連の批判が目立つが、それはそれとして。
個人的に低反発バットの影響で戦術が変わってきている旨に関してはめちゃくちゃ共感できる。
なので、今回は(も)そこについて適当に言っていくことにする。
一発勝負の甲子園を勝ち抜くのに重要な要素。タイプの違う好投手2人を擁した沖縄尚学
まず何度も連呼している通り一発勝負の甲子園は半年かけて140試合以上を消化するプロ野球とはまったくの別もの。
短期決戦の極みのような緊張がずーっと続く。
その中で感じたのが、
・打撃力
・一線級のピッチャー2人
・内野の守備力
を兼ね備えるチームは強いということ。
2025年夏の甲子園。広陵高校きっかけで観てるけどおもしろいね。一発勝負のトーナメントで優勝するチームの条件を3つ挙げてみる。僕の中での優勝候補は…
当たり前だが打てるチームは相手よりも点を多く取れる。
低反発バットの導入で打球が飛ばない中、一定以上の打力のあるチームは明らかに強い。
また昨今の風潮からスーパーエースが命を削りながら1人で投げ抜くようなチームはかなり減った。
トーナメントを勝ち抜くには複数のピッチャーをどう運用するかが重要で、タイプの違う好投手を2人擁するのが理想に思える(沖縄尚学もこれ)。
内野の守備力はマジで大事。“普通にアウトが取れる”ことがアドバンテージになる
そして3つ目の内野の守備力。ここはマジで大事。
今大会ではランナーを背負った場面での内野のミス(or記録上はミスではないプレー)によってピンチが広がる、得点が入るシーンを嫌というほど目にした。
準決勝、決勝の大一番でもそういうプレーはマジで目につく。
つまり、プロに比べて守備力が劣る高校生にとって「普通の内野ゴロを普通にアウトにできる能力」はそれだけでアドバンテージとなる。
送りバントを多用する理由が興味深い。チャンスを広げるというよりダブルプレーを避けるため
上記の記事内で僕がもっともおもしろいと思ったのが「「送りバント」は最高の戦術? ここ15年で最多に」の件。
送りバントの多さは僕も感じていて、たとえばワンアウト1塁の状況でも普通に送りバントのサインが出る。
あえてツーアウト2塁にするより普通に打った方がいいのでは? と僕などは思うのだが、どうやらそうではないらしい。
理由がまた興味深い。
送りバントを多用するのは「チャンスを広げるという意味合いより、ダブルプレーで相手に流れを渡したくない」(山梨学院吉田洸二監督談)から。
低反発バットの導入で打球が内野の正面を突くケースが増えた。
競った展開では特に送りバントが決まるか決まらないかで流れが変わってくる。
あ~、なるほど。
そういうことね。
僕は先日も申し上げたように送りバントの多用は選手個々の力量差が大きいためだと思っていた。
2025年夏の甲子園準決勝2試合、全然予想がつかねえw 戦力的にも勢い的にも山梨学院かな? と思うけど、県立岐阜商業の例もあるし。高校野球はホントにわからん。そしてめちゃくちゃおもしろい
中心打者とそれ以外の打者ではヒットを打つ確率が格段に違う。
飛び抜けた選手が1人いれば、いかにその選手の前にランナーを溜めるかがカギになる。
いわゆるチーム内での序列によるところが大きいのだろうと。
ところが実際には低反発バットの影響で戦術自体が様変わりしていたという。
「低反発バットに変わって大量得点が望めなくなり、1点をめぐる攻防にシフトチェンジするようになってから、各チームの戦術や戦略が変わってきている」
内野の守備力強化は今後さらに進むと予想。急務のタイブレーク対策もやはり守備から?
低反発バットの導入によって
・内野ゴロの数が増える
・送りバントが多用される
ことを考えると、内野守備の重要性は今後さらに増していくはず。
最初に挙げた“強いチームの条件3つ”の優先度としては、
内野の守備力>>ピッチャー2人>>>>打撃力
という感じ。
才能がモノを言う投手力や打撃力に比べて守備は“やればやるほど”上達する。次回以降も各チームが優先的に強化していくと予想する。
またこれも前回申し上げたが、タイブレークの対策は間違いなく急務。
第107回夏の甲子園。沖縄尚学が日大三高に勝って初の夏優勝。サウスポーのアドバンテージ、内野守備の重要性、タイブレークの攻略。大会を通して思ったことをあれこれ言っていく
各チームが1点を取りにいく戦略にシフトしたことで今大会は過去最多となる8試合がタイブレークにもつれ込んでいる。ここをいち早く攻略したチームが頭一つ抜けることができるのではないか。
「最遅」試合更新、タイブレーク最多に出場辞退…夏の甲子園総括https://t.co/WoLj2akMKY
夏の甲子園は沖縄尚学が初優勝。大会史に刻まれる出来事や異例の事態も発生しました。
— 毎日新聞 (@mainichi) August 23, 2025
と言っても、正直できることは限られている気もする。
先攻側は先頭打者が送りバントをするか普通に打つかの二択、それを打順によって変えるくらい。
何だかんだで緊迫した場面で内野ゴロを確実にアウトにできることがもっとも重要だと思っている。
藤浪晋太郎が初勝利。中日が2戦連続で主力を出さず左打者だらけの打線を組んだことへの感想を。井上監督「ベストオーダーを組めない」、藤浪「好きなだけ嫌がってください」。真剣勝負の最中に日和って自分で弱点晒してんじゃねえよ
改めて高校野球とプロ野球は別もの。ドラフト指名された高校生が活躍できるまでに数年を要するのも納得
送りバントの多用、タイブレーク対策、低反発バット。
繰り返しになるが、一発勝負の高校野球はプロ野球とは似て非なるもの。ドラフト指名された高校生がプロで活躍できるまでに数年を要するのも納得である。
要は日本のプロ野球からメジャーに行った選手が「まったく競技が違う」と感じるのと同じ。
想像を超える苦労の末に一軍の舞台に立っているのだろうと。
ちなみに僕は低反発バットの導入で将来的な学生野球の小粒化→国際舞台での弱体化を懸念している。
大谷翔平背番号17 野球 Tシャツ ジャージ ユニフォーム 野球ユニフ半袖
侍ジャパン 番號18 山本 由伸 野球応援 フェイスタオル
今永昇太のピッチングバイブル