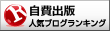第107回夏の甲子園。沖縄尚学が日大三高に勝って初の夏優勝。サウスポーのアドバンテージ、内野守備の重要性、タイブレークの攻略。大会を通して思ったことをあれこれ言っていく【感想】

2025年8月23日に甲子園球場で行われた第107回全国高校野球選手権大会決勝戦。沖縄尚学vs日大三高戦は3-1で沖縄尚学が勝利、初の夏甲子園優勝を飾っている。
#第107回全国高校野球選手権大会
107回目の夏、頂点に輝いたのは…◤ #沖縄尚学 ◢
夏の甲子園 初優勝!
15年ぶりに沖縄勢が頂点に!🔻最新情報は #バーチャル高校野球 で!https://t.co/SVfCjamlUs#高校野球 #甲子園 pic.twitter.com/aTjkVISZ2F
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) August 23, 2025
8月1日からスタートした夏の甲子園。
僕は普段あまり高校野球は観ないのだが、広島の広陵高校の一件で注目した次第である。
で、おもしれえなコレと。
きっかけはネガティブだったが高校野球自体はめちゃくちゃおもしろい。
プロ野球との競技性の違いから優勝予想まであれこれ考え、大ハズシした笑
2025年夏の甲子園。広陵高校きっかけで観てるけどおもしろいね。一発勝負のトーナメントで優勝するチームの条件を3つ挙げてみる。僕の中での優勝候補は…
正直、沖縄尚学はベスト4に残った中ではもっとも小粒かと思ったのだが。
一発勝負のトーナメントの難しさ、高校野球のドラマ性に翻弄されまくる数日間となったw
沖縄尚学優勝おめでとうございます。
日大三高もナイスゲーム。「広陵きっかけでチラ見→何だコレ、高校野球超おもしれえ!!」っていうひん曲がった流れでしたが、最高に楽しい夏の甲子園でした。
— 俺に出版とかマジ無理じゃね? (@Info_Frentopia) August 23, 2025
甲子園を観て思ったこと3点。改めてプロ野球とは別競技だなと
まず今回の甲子園を観て思ったのが、
・サウスポーのアドバンテージの高さ
・内野守備がめちゃくちゃ重要
・タイブレークの対策が進むのでは?
の3点。
一発勝負のトーナメントは僕が普段観ているプロ野球とはまったく別物。
さらに高校生はプロに比べて技術的にもメンタル的にも未熟な部分が多い。チーム内でも格差が大きくプロに注目されるような選手とそうでない選手では求められる役割が違う。マジで違う。
なので、近年プロでは“否”とされる送りバントや盗塁といったプレーも十分機能する。
長いシーズンをトータルで考えるプロと違い、「この試合に勝つために今何をすべきか」を判断する瞬発力、柔軟性が問われる。
田中将大通算199勝目!! 神宮で巨人vsヤクルト戦を現地観戦してきたぞ。まっすぐに力があった田中。でも5回でアップアップになるのもいつも通り。そしてボールがアホみたいに飛ぶ。現地で改めて思った
サウスポーのアドバンテージの高さ。右オーバースローはプラスアルファが必須
そして上記の1点目「サウスポーのアドバンテージの高さ」について。
これはそのままの意味で、高校野球レベルではピッチャーは左投げというだけで希少性が高い。
140km前後のまっすぐをゾーンに安定して放れればある程度やれる、チェンジアップとスライダーを両サイドに投げ分けることができれば間違いなく超高校級になれる。
それこそプロに入れば“左で投げてるだけの人”になってしまうピッチャーでも甲子園の舞台では十分活躍できる。
逆に右ピッチャー(オーバースロー)は求められる水準が一気に上がる。
先日申し上げたようにアベレージで130km後半、MAX140km半ばみたいなピッチャーはベスト8、ベスト4レベルの打者にとっては一番打ちごろ。
プラスアルファがなければあっという間に捕まってしまう。
そういう意味では沖縄尚学の左右エースは理想的だった。
決勝戦で先発した新垣投手は球速は140kmちょいだが大きく落ちる縦スラがある。
さらにセットポジションから足を上げて一瞬止まる→そこからいきなり投げ込むのでタイミングも取りにくい。真上から投げ下ろす縦振りのフォームも相まって「右オーバースローにはプラスアルファが必要」という条件を見事に満たしていた。
エースナンバーを背負う末吉投手に関しては好投手の条件をすべて兼ね備えていた(と思う)。
力感のないフォームから手元で“ピュッ”とくる系のまっすぐにスライダー、カーブ、フォーク。制球力もある。
サウスポーというアドバンテージだけでなく普通にハイレベルなピッチャーだった。
ベスト4の中でもっとも小粒だと思った沖縄尚学だが、終わってみればこの両投手の存在が際立っていたなぁと。
2025年夏の甲子園準決勝2試合、全然予想がつかねえw 戦力的にも勢い的にも山梨学院かな? と思うけど、県立岐阜商業の例もあるし。高校野球はホントにわからん。そしてめちゃくちゃおもしろい
サウスポーに異様に強かった山梨学院。大会屈指のサウスポーに自分のピッチングをさせない打線
なお準決勝で沖縄尚学に敗れた山梨学院はサウスポーに強いという特異点だった。
1回戦で聖光学院の大嶋投手を粉砕、2回戦では岡山学芸館のリリーフ田路投手を打ち崩して勝負を決め、準々決勝では京都国際のエース西村投手を攻略、準決勝では上記の末吉投手から6回までに4点を奪っている。
特に準々決勝の西村投手、準決勝の末吉投手は今大会を代表するサウスポー。この両投手に自分のピッチングをさせなかったのはマジですごい。
ちなみに怪物2年生と言われた菰田投手はそこまでぶっ飛んだものは感じなかった。
もちろんまだ2年生なのでアレだが、たとえば藤浪晋太郎や佐々木朗希ほどのスペシャル感は(現時点では)ない。
もっともイメージが近いのは元楽天イーグルスの安樂智大(済美高校)だろうか。
夏の甲子園(2025年)振り返り。送りバントを多用する理由が興味深い。「チャンスを広げるというよりダブルプレーを避ける意味合いが強い」んだって。今後内野守備の重要性はさらに高まるのでは? 才能がモノを言う投手力、打撃力より上達しやすい
内野守備の重要性。低反発バットの導入で「普通のゴロを普通にアウトにできる」ことがアドバンテージになる
2点目の「内野守備がめちゃくちゃ重要」に関しては低反発バットの影響が大きい。
先日も申し上げた通り高校生はプロに比べて守備力が大きく劣る。
今大会でもエラー(記録上はそうでなくても)が点に結びつくケースは何度もあった。
ピンチの場面で固くなってしまうのだと思うが、大事な場面でのエラー、「そこを防げていれば」というプレーで試合展開がガラッと変わるのも高校野球の特徴である。
そして低反発バットの導入によって内野に打球が飛ぶケースが増え(たぶん)、それに伴い内野守備の重要性も爆上がりした印象。
下記によると「低反発バットは芯で当たれば従来のバットよりも飛ぶ」とのこと。
低反発バットへの順応「芯で捉えれば飛ぶ」 本塁打すでに前回に並ぶ https://t.co/k0L3P9LpqP
— 朝日新聞スポーツ (@asahi_sports_) August 17, 2025
逆に言うと芯に当たらなかった場合はボテボテのゴロになりやすいわけで。
さらにフライが伸びないとのことなので、やはり内野の守備機会は増えることが想定される。
つまり「普通のゴロを普通にアウトにできる」守備力はそれだけでアドバンテージになる。
実際の試合を観てもそこはめちゃくちゃ感じた。
タイブレーク対策は急務。ここにいち早く対応したチームが頭一つ抜ける?
3点目の「タイブレークの対策が進むのでは?」も大会を通して思ったこと。
タイブレークは2023年春以降、10回からの適用となったルールだが、ここの対策はマジで急務ではないか。
勝ち上がればそれだけ拮抗した試合も増える。低反発バットの導入もあって1イニングに大量得点が入るケースも少なくなる(と思う)。
つまりタイブレークをいかに攻略するか、どれだけ効率よく得点するかはマジで重要。
ノーアウト1、2塁では送りバントが最適解なのか。打順によってはそのまま打たせる方がいいのか。
もしくは思い切ってヒットエンドランや盗塁等でノーアウト2、3塁を狙うのか(さすがにそれはないか)。
先頭打者は転がしてダブルプレーになるより三振の方がマシだし、狙ってフライが打てるならそうするべき。
しかも相手も同じ状況でスタートするので先行側は1点取ればいいわけではない。
そう考えると、やはり先頭打者は送りバントが定石になるのか?
などなど。
いろいろな対策が考えられるが、今のところ各校とも手探りな印象である。
今井達也がすごすぎる。完全に日本最強ピッチャー。2025年3月の侍ジャパンで「何だコイツ!?」ってなった。今シーズンオフにMLBに行け。チーム成績関係なくいい感覚を掴んだときに行くべきですよ
制度自体の是非もあるがそれはそれ。
導入されたからにはやるしかない。
今後数年でタイブレークにうまく対応できたチームが頭一つ抜ける可能性が高いのではないか。
まあ、ぶっちゃけやれることは限られているとは思うが。
大谷翔平背番号17 野球 Tシャツ ジャージ ユニフォーム 野球ユニフ半袖
侍ジャパン 番號18 山本 由伸 野球応援 フェイスタオル
今永昇太のピッチングバイブル