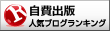2025年夏の甲子園。広陵高校きっかけで観てるけどおもしろいね。一発勝負のトーナメントで優勝するチームの条件を3つ挙げてみる。僕の中での優勝候補は…

第107回全国高校野球選手権大会が続いている。
2025年8月5日に開幕した“夏の甲子園”は本日(8月16日)に大会11日目を終えた。
明日以降、3回戦の残り4試合が終わるとベスト16、そこから準々決勝、準決勝、決勝と続いていく。
第107回夏の甲子園。沖縄尚学が日大三高に勝って初の夏優勝。サウスポーのアドバンテージ、内野守備の重要性、タイブレークの攻略。大会を思ったことをあれこれ言っていく
広陵高校きっかけで久しぶりに甲子園を観ている。って、1回戦が終わって辞退は悪手すぎるでしょ
僕は普段あまり高校野球は観ないのだが、今大会はぼちぼち楽しく観戦している(テレビで)。
理由ははっきりしていて「広陵高校の件があったから」。
正直、程度はともかく運動部での過度な上下関係や暴行は普通にあると思っている。
確かに広陵高校のアレは過激だったが先輩部員が後輩を“かわいがる伝統”にそこまで驚きはない。
そして、実態が明るみに出た以上広陵は出場を辞退すると思っていたら……。
まさかの強行出場。
で、1回戦に勝利してからの辞退という謎ムーブである。
いやいや、マジかよ。
それだと全国放送で顔と名前を晒しただけになっちゃうじゃん。
出場すると決めた以上、反響の大きさは覚悟の上だったんじゃないの?
ここまで大ごとになればどの道野球部としてはお先真っ暗である。
つまり、出ると決めたのなら最後まで突き進むしかなかったわけで。
広陵高校出場辞退、しょーもない。
野球部だけじゃなく多方面に影響が出るなんて今のご時世を考えれば容易に想像ついただろ。
当事者も周りの大人もそれを受け止める覚悟で出場したんちゃうんか。出るって決めたならとことん行き切るしかなかったんだよ。
中途半端な覚悟で日和ってんじゃねえよ。 https://t.co/SCzZid77FE— 俺に出版とかマジ無理じゃね? (@Info_Frentopia) August 10, 2025
そんな中、多くの方がおっしゃるように2回戦の前の辞退は考えられる中での一番の悪手。
個人的には全国優勝してカメラに中指立ててやろうくらいに腹を括っていると思っていたのに。
ちなみに本日下記の記事が出ている。
広陵高校野球部・元部員の衝撃告白「部室での暴行で右半身が麻痺し、車椅子生活に」https://t.co/hcojA3VBsA#週刊文春
— 週刊文春 (@shukan_bunshun) August 16, 2025
文春としては2回戦が終わるタイミングで爆弾を投下するはずが、当事者はすでに雲隠れした後という。
下世話な週刊誌の目論見を外したという意味では唯一いい判断だったかもしれない(なお内容)。
そんな感じで、広陵高校きっかけで夏の甲子園を久しぶりにちゃんと観ている。
2025年夏の甲子園準決勝2試合、全然予想がつかねえw 戦力的にも勢い的にも山梨学院かな? と思うけど、県立岐阜商業の例もあるし。高校野球はホントにわからん。そしてめちゃくちゃおもしろい
長丁場のプロ野球とはまったくの別物。バントや盗塁を多用。瞬発力と柔軟性が大事なんだろうね
まず久しぶりに甲子園を観て(全部じゃないけど)思ったのが、プロ野球とはまったくの別物だなということ。
ピッチャーの球速やストライクゾーンの広さ、守備力といった単純な話ではなく勝ち進むための戦術的な部分で。
半年かけて140試合以上をこなすプロと違い、高校野球は負けたら終わりの一発勝負。
「長いシーズンをトータルで考えて〜」よりも「今この瞬間、勝つために何をすべきか」の方が優先される。
ピッチャーがバタバタしているときの盗塁は間違いなく有効だし、ヒット&ランは心理的な揺さぶりにめちゃくちゃ役立つ。
プロの世界ではデータ上“否”とされる作戦も、一発勝負&技術や精神が未熟な高校野球では“可”になる場合もある。
近年プロ野球では機械的な送りバントを毛嫌いする傾向がある。
中でも浅い回ではワンアウトと引き換えに2塁にランナーを進めるよりも“打てる2番”を配置するケースが多い。
統計的にもその方が得点効率がいいとも言われている。
だが、高校野球ではそのバントが普通に多用される。
それこそツーアウトにしてでもランナーを進めるシーンを何度観たか。
要は個の力の差が大きいのだと思う。
チームで飛び抜けた存在(大黒柱)がいれば、どうしてもその選手に頼ることになる。
当然そういう選手は中軸を打つわけで、勝つためにはいかにその選手の前にランナーを貯めるかが重要になる。
結果、ツーアウトにしてでも先の塁を目指す方が勝率が上がるのだろうと。
もちろん個の力だけでなくその日の調子や相手ピッチャーとの相性を考えての判断もある(はず)。
セオリーや“自分たちの野球”をベースに、瞬発力と柔軟性が問われるのが一発勝負のトーナメントなのだと思う。
田中将大3ヶ月ぶりの一軍登板で5.2回2失点(自責1)。5月に比べて出力も上がって変化球もキレてた。今年一番よかったけど、QSに届かない。根本的に球威が足りてない。これが田中の現在地なんだろうな
僕が思う優勝するチームの特徴を3つ。大前提として打てること
ではここからは僕が思う“優勝する(に近づく)チームの特徴”を挙げていくことにする。
1つ目は大前提として打てること。
野球は点を取られなければ負けないスポーツだが、勝利条件が「相手よりも1点でも多く取ること」の時点で得点力の重要性は明らかである。
そして、いわゆる強豪校と呼ばれる学校はここが違う。
パッと見でわかるスイングの鋭さ、ピッチャーがわずかでも疲れを見せるとあっという間に打ち始める隙のなさ、終盤の集中力や勝負どころでの驚異的な粘り、などなど。
冗談抜きで「ここで打ってほしい」というシーンで打つ胆力は日本野球の一番の持ち味かもしれない。
今日(8月16日)の第3試合、京都国際の逆転劇などはまさにそれ。
7回裏をエースが無失点で切り抜けてリズムを作り、8回表にツーアウト2、3塁から2点タイムリーで逆転。
尽誠学園のピッチャーに疲れが見えた途端にひっくり返した攻撃はマジでお見事だった。
夏の甲子園(2025年)振り返り。送りバントを多用する理由が興味深い。「チャンスを広げるというよりダブルプレーを避ける意味合いが強い」んだって。今後内野守備の重要性はさらに高まるのでは? 才能がモノを言う投手力、打撃力より上達しやすい
守備力はどう考えても大事。プロよりも落ちるからこそ差がつきやすい
また得点力と同じくらい大事なのが守備力。
当たり前だが、プロ野球に比べれば高校生は守備力が格段に落ちる。
中継を観ていても「え? それ捕れない?」「そこを落とす?」というプレーが多々ある。
また送球の正確性やポジショニング等、記録に現れない稚拙さは即得点につながる。
ここはピッチャーの球速以外でプロとの差をもっとも感じる部分かもしれない。
つまり、守備が固いチームはそれだけで強豪の条件を満たすことになる。
メンタルがプレーに及ぼす影響が大きい高校生にとって、守備力の高さは安心感につながる。
逆に守備の乱れで失点した際の精神の揺れもプロとは比較にならないと想像する。
上記の京都国際や17日に沖縄尚学と対戦する仙台育英などはちょろっと観ただけでもわかるくらい守備力が高かった。
藤浪晋太郎が初勝利。中日が2戦連続で主力を出さず左打者だらけの打線を組んだことへの感想を。井上監督「ベストオーダーを組めない」、藤浪「好きなだけ嫌がってください」。真剣勝負の最中に日和って自分で弱点晒してんじゃねえよ
もっとも重要なのは投手力。エース級が2人ってのが理想じゃない? 3人だとむしろ…
表題の通りだが、甲子園を勝ち抜く上でもっとも重要なのはやはり投手力。
条件としてはエース級が2人というのが最適解だと思っている。
近年は複数のピッチャーを運用するケースが増え、スーパーエースが命を削りながら1人で投げ抜く光景はほぼなくなった。
温暖化の影響でシャレにならないくらい暑くなっていることを考えても「全試合を1人で投げ抜く!!」ようなピッチャーは今後も減っていくと思われる(1人のピッチャーは1週間で500球以内というルールもできた)。
その中でいいピッチャー(先発で試合を作れる)を2人擁するチームは強い(と思う)。
超高校級のエースと、超高校級ではないが他校に行けば十分エースになれる控え、それも左右分かれているのが理想。
この2枚看板を交互に起用しながら準々決勝、準決勝までにどれだけ余力を残せるか。
あまり乗れなかったMLB東京シリーズ。大谷翔平は大スターだけど。極端すぎるドジャース野球と偏った報道にうんざりした。平均視聴数2500万人でも野球に興味があるのは…
そして、ハイレベルなピッチャーが3人いる場合は逆にうまくいかない気がする。
各ピッチャーをローテーションで先発させる、もしくは継投で起用していくことになるわけだが、不調のピッチャーが1人いればそこから試合が壊れる可能性が生まれる。投手交代が増えればそれだけ危険が増す。
いわゆる“ガチャ要素”が高くなるというヤツ。
8月13日に京都国際に敗れた健大高崎がまさにそんな感じ。
プロ注目のエースを温存した結果、5回までに5点を取られて主導権を握られた。
もともと健大高崎は怪我を避ける起用を心がけるチームらしいが、仮に甲子園で通用するピッチャーが2人しかいなかった場合は違う采配になっていたかもしれない。
以上の条件を満たす学校として、僕の中での優勝候補は京都国際、横浜、仙台育英の3校。
安定感や試合運びの横綱っぷりが他チームに比べて一段抜けている(と思う)。
大谷翔平背番号17 野球 Tシャツ ジャージ ユニフォーム 野球ユニフ半袖
侍ジャパン 番號18 山本 由伸 野球応援 フェイスタオル
今永昇太のピッチングバイブル